
システム理論入門―ニクラス・ルーマン講義録〈1〉 (ニクラス・ルーマン講義録 1)
- 作者: ニクラスルーマン,ディルクベッカー,Niklas Luhmann,Dirk Baecker,土方透
- 出版社/メーカー: 新泉社
- 発売日: 2007/04/01
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 18回
- この商品を含むブログ (35件) を見る
触れられている内容は多岐に渡るも、やはり若干駆け足気味で「あとは自力でやってね(はあと)」という感じ。でもルーマン知ろうと思って最初に読むなら、やっぱこの2冊がいいんじゃないかと愚考する次第。
もうちょっと時間を置いてから再読しようかな
以下メモ
ホワイトヘッドは近代ヨーロッパにおいて生まれた機械論的自然観の問題性を浮き彫りにし、それが「抽象を具体とおき違える錯誤(the fallacy of mis−Placed concreteness)」にもとづくことを指摘している。彼は、17世紀の哲学から現代哲学が引き継いだ機械論的自然観を分析し、それに代わるものとして、有機体論的自然観を提唱した。この着想は『過程と実在』の「有機体の哲学(philosophy of organism)」として体系的な形で示されることとなる。有機体の哲学は、近代の自然科学の勃興によって廃れてしまった形而上学の構図を現代の先端的な科学の領域を媒介することによって復活させようとする試みであった。著作において、近代の単なる人間中心的な考えかたを改め、人間がその環境世界(自然)と人間を越える存在(神)とに深くかかわる事によって初めて人間たりうるという基本的な観点が貫かれている。
また、バートランド・ラッセルとの共著『プリンキピア・マテマティカ』(Principia Mathematica、『数学原理』)はよく知られている。ホワイトヘッドの哲学としては、世界をモノではなく、一連の出来事(event)つまり、過程として捉える特徴がある。この哲学は、プロセス哲学あるいはプロセス神学として知られており、現在もその考え方を受け継ぐものがおり、現代思想の一翼を担っている。また、プロセス哲学の研究者は、ホワイトヘッドの哲学とエコロジー思想と密にし、環境問題にも関わっている人物も多いが、これもホワイトヘッドの哲学が有機体論的自然観に基づいているからに他ならない。 さらにホワイトヘッドのこの考えは、宗教哲学にもおよびプロセスとしての神概念や宇宙を説く観点から「コスモロジーの哲学」という捉え方もできる。これは、主著『過程と実在』の副題である「コスモロジーへの試論」にもあらわれている。その独特の有神論的な哲学思想は、現在もなお様々な研究者によって、挑戦されている哲学でもある。
アルフレッド・ノース・ホワイトヘッド - Wikipedia
グレゴリー・ベイトソン(Gregory Bateson, 1904年5月9日 - 1980年7月4日)は、イギリス生まれ、第二次世界大戦中にアメリカ合衆国に渡った、アメリカ合衆国の人類学・社会学・言語学・サイバネティックスなどの研究者。遺伝学者ウィリアム・ベイトソンの息子。文化人類学者マーガレット・ミードの公私にわたるパートナーでもあった。 イルカのコミュニケーションの観察や精神病院でのフィールドワークから、「ダブルバインド」という概念で象徴される独自のコミュニケーション理論を構築した。
グレゴリー・ベイトソン - Wikipedia
ウィキペにフォン・フェルスターの項がないだと!?
システム理論(ないしサイバネティクス)における構成主義は、知覚にかんする実験や神経生理学の知見からはじまった。たとえばフォン・フェルスターは、「現実の構成について」という論文の中で、「われわれの知覚する環境は、われわれの発明である」というテーゼを提示し、システムの認知=意味構成が再帰的作動の閉じたサイクルの中で、自己言及的に行われることを示した。
いうまでもないことだが、これは、システムが環境からの刺激ないし入力を(たとえば熱力学的に閉じたシステムと同じ意味で)まったく受けつけない、ということではない。刺激ないし入力はシステムの作動に一種の撹乱をあたえはするが、けっしてシステムの作動を因果的に規定しない、ということである。マトゥラーナの用語でいえば、システムは環境との構造的カップリングの中で認知=意味構成を行う、ということになる。
システム理論の構成主義的意味論 - 徳安 彰
一般システム理論は、早くから研究者が組織や相互依存の関係を述べる為に使われていた学名であった。部分から部分の組織まで;「構成要素」から「動的関係」まで移行する[1]という点で、このシステムの考えは古典的な還元主義(その主題として一つの部分を持っている)の見地と対照的である。システムは、規則的に相互作用するか、あるいは、一緒になるとき、新しい全体を構成する活動/部分のグループを相互に関係づけられ構成される。ほとんどの場合、この全ては構成要素に見いだされることができない特性を持っている。
ルートヴィヒ・フォン・ベルタランフィ財団の文章の中で、一般システム理論のシステムの構想は、1600年代のゴットフリート・ライプニッツやニコラウス・クザーヌスの哲学や彼の対立者の一致(Coincidentia Oppositorum)からたどる事が出来る。複雑さ、自己組織化、結合説、適応システムといった議題は、既にノーバート・ウィーナーやウィリアム・ロス・アシュビー、ジョン・フォン・ノイマンとハインツ・フォン・フェルスターのような研究者を通して1940年代から1950年代に、人工頭脳学に近い分野で研究されていた。彼らは、最新の道具を用いず、鉛筆、紙、計算を用いて複雑なシステムを調べたという。
システム理論 - Wikipedia
↑この項要再読
1901-01-02 - suneoHairWax
スペンサー・ブラウンについて - ルーマン・フォーラム - 日曜社会学
ルーマン・フォーラムなんてあったのね

- 作者: タルコット・パーソンズ,佐藤勉
- 出版社/メーカー: 青木書店
- 発売日: 1974/01/01
- メディア: 単行本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (6件) を見る
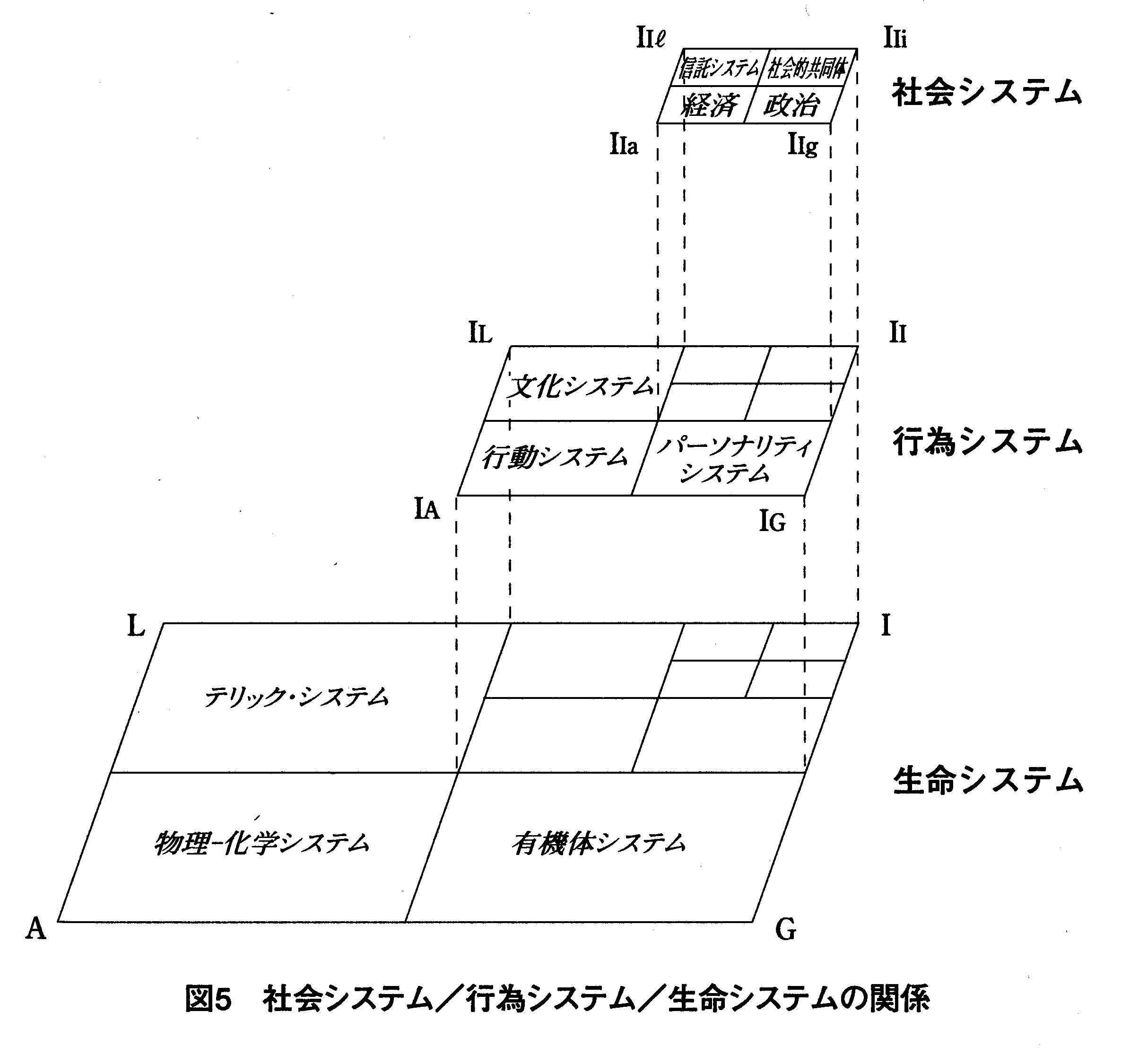
晩年のパーソンズによるルーマン批判 : 関本洋司のブログより拝借
- 均衡概念
ハンガリーの経済学者コルナイの自伝。ハンガリー語では、日本語と同じように姓・名の順に書くので、コルナイ・ヤーノシュが正しい表記だ。バルトークも本来はバルトーク・ベーラ、フォン・ノイマンもノイマン・ヤーノシュである。
経済学者の伝記がおもしろい本になることはまずないが、本書は例外である。1928年生まれの著者の人生は、20世紀の社会主義の運命とそのまま重なる。著者は共産主義者として青春を過ごし、戦後はハンガリーの社会主義政権のもとで、ナジ首相のスピーチライターもつとめた。しかしハンガリーの民主化運動は、1956年にソ連の軍事介入によって弾圧された。著者はマルクス主義と決別し、政治の世界を離れて研究者になる。
著者は、線形計画法を使って計画経済を効率化する研究を行う。特に1965年に数学者リプタークとの連名で発表した"Two-Level Planning"(Econometrica)は、社会主義の計画プロセスを一般均衡理論と本質的に同一のモデルで記述した古典として有名だ。これは、さほど驚くべきことではない。ワルラスの一般均衡理論は、もともと社会主義経済のモデルであり、模索過程を模擬する「分権的社会主義」は、1930年代にオスカー・ランゲが提唱していた。ただ実際に社会主義経済を運営するアルゴリズムを提案したのは、コルナイ=リプタークが初めてである。
しかし、コルナイ=リプターク・モデルを計算機に実装して経済運営を行う実験は失敗した。その最大の原因は、計算を行うための情報が欠如していたことだ。計算の過程で、各部門が中央当局に正確な情報を上げるインセンティヴはないので、情報は歪められ、あるいはまったく上がってこない。こうした実験を通じて、著者は一般均衡理論が情報コストを無視した非現実的なモデルであることを(図らずも)実証し、新古典派経済学を批判するAnti-Equilibrium(1968)を書く。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/b6ef33327a69b1008011756278ccbbd1
池田信夫先生じゃないですか!

- 作者: コルナイヤーノシュ,Kornai J´anos,盛田常夫
- 出版社/メーカー: 日本評論社
- 発売日: 2006/06/01
- メディア: 単行本
- クリック: 20回
- この商品を含むブログ (33件) を見る
- ヤーノシュ
- 社会主義=生産<需要
- 資本主義=生産>需要
p60?あたりで一般システム理論の概説
- 均衡モデル
- エントロピー(自閉、閉じたシステム)
- 開放システム(I/Oモデル)
- 進化理論
- ブラックボックス
- サイバネティクス(フィードバック・モデル)
- 制御理論
- 行為理論
- セカンド・サイバネティクス(ポジティブ・フィードバック)
- 自己言及(オートポイエーシス)システム(閉鎖)
- 差異理論
俺の拙い理解だとオートロジカル(自己理論的)じゃない理論だと「何がシステムかという問いに答えられない」からダメよってことなのかな。このへんがキモなんだろうけどよくわかんねえや
- 自己理論(オートロジカル)=わたしの客体に成り立つことはわたし自身にも成り立つ
p.62
批判を評価したいのであれば、批判対象の側を観察するのではだめで、批判者を観察することによってどのようなシステムがそのような批判を行っているのかを見る方がはるかに望ましい
- p.71 "システムは差異である"

- 作者: G・スペンサー=ブラウン,大澤真幸,宮台真司
- 出版社/メーカー: 朝日出版社
- 発売日: 1987/03
- メディア: 単行本
- クリック: 11回
- この商品を含むブログ (11件) を見る

- 作者: ガブリエルタルド,Jean‐Gabriel Tarde,池田祥英,村澤真保呂
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2007/09
- メディア: 単行本
- クリック: 30回
- この商品を含むブログ (27件) を見る

- 作者: ガブリエルタルド,村澤真保呂,信友建志
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2008/12/18
- メディア: 単行本
- クリック: 23回
- この商品を含むブログ (6件) を見る
-
- ルネ・ジラール

- 作者: ルネ・ジラール,古田幸男
- 出版社/メーカー: 法政大学出版局
- 発売日: 1982/11
- メディア: 単行本
- クリック: 14回
- この商品を含むブログ (8件) を見る

欲望の現象学―ロマンティークの虚像とロマネスクの真実 (叢書・ウニベルシタス)
- 作者: ルネ・ジラール,古田幸男
- 出版社/メーカー: 法政大学出版局
- 発売日: 1971/01
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 15回
- この商品を含むブログ (11件) を見る
- ベイトソン "情報とは「一つの差異を作る一つの差異」"
- p.77 自己言及(観察)と差異に違いはない
システムはそれが存続するとき、システムと環境の差異を再生産しコミュニケーションを通じてコミュニケーションを再生産するために唯一の作動を、唯一の作動タイプを必要とする
- 再参入 re-entry
ヤーコプ・ヨハン・ユクスキュル(Jakob Johann Baron von Uexküll、1864年9月8日 ケブラステ) - 1944年7月25日 カプリ島)は、エストニア出身のドイツの生物学者・哲学者である。
それぞれの動物が知覚し作用する世界の総体が、その動物にとっての環境であるとし、環世界説を提唱。動物主体と環世界との意味を持った相互交渉を自然の「生命計画」と名づけて、これらの研究の深化を呼びかけた。また生物行動においては目的追求性を強調し、機械論的な説明を排除した。ユクスキュルの生物学はマックス・シェーラーやヘルムート・プレスナーをはじめ当時の西欧知識人の人間観に多大な影響を与え、「新しい生物学の開拓者」と呼ばれた。
ヤーコプ・フォン・ユクスキュル - Wikipedia
だめだ、メモがなげぇ…疲れてきた…
2010.08.25 Wed.追記
- G.H.ミード
ジョージ・ハーバート・ミード (George Herbert Mead、1863年2月27日 - 1931年4月26日) は、アメリカの社会心理学者。哲学者、思想史家でもある。研究業績の多くを、シカゴ大学で行い、プラグマティズムの重要な一人として知られている。ミードは、シンボリック相互作用論の父として知られている。プラグマティズムの大家、ジョン・デューイとの共同研究も知られているところである。
ジョージ・ハーバート・ミード - Wikipedia一人ではできず、数人の協力で成り立つ行動を「社会的行動」と呼び、そのような行動が働きかける対象を「社会的対象」と呼ぶことにする。この「社会的対象」は多くの違った個人のそれぞれの異なった行為に対して応える性格を持つ。「社会的対象」はそれと関わる個人の行動が、もう一人別の個人にとってはっきり見えている場合にしか成立しない。ある人が「財産」を持っていて、その財産が他の人にとってどういう意味を持ち、どう関わり合うのかを理解したときに初めて、その「財産」は「社会的対象」となるのである。「自我」は、ある個人が自分以外の他人の役割を想像できるときに、初めて発生する。自分以外のメンバーがどのような行動をするかの傾向を知り、また自分がどのように行動すれば他のメンバーによって「正しい」と見なされるかも知っている。つまりその時、「自我」は自分にとって一つの「社会的対象」となる。
相手からある種の反応を引き出すために使われた「音声をともなう身振り」が、人間集団に共有されるようになると、それは社会のメンバーにとって共通の意味を持つ「象徴」となる。この「象徴」を産み出すメンバーの協力は、共同の労働を可能とし、さらに複雑な「象徴」の組み合わせが進み、「言語」となる。言語による会話が個人の内面に持ち越されたものが「思想」であり、すべての思想の根底には「身振り」がある。身振りが「自覚された意味を持つ象徴」まで高まると、それは「社会的対象」として一定の広さの社会集団を組織することができる。個人が他人と協力して行うことについて、自分以外の個人の役割をも考慮して、おたがいに行動を統制するようになる。このような「社会的対象」の範囲を更新し拡げることで、地球大の社会性さえ獲得することができよう。
「自我」とは自覚されたときから社会の場にいる、つまり「孤立した自我」は本来の自我の状況ではないというのが、ミードの立場である。「個人」「経験」「精神」はコミュニケーションをとおして出現する。こうしたミードのコミュニケーション論を、デューイが教育・芸術に応用した。

- 作者: G.H.ミード,George Herbert Mead,稲葉三千男,中野収,滝沢正樹
- 出版社/メーカー: 青木書店
- 発売日: 2005/03
- メディア: 単行本
- クリック: 20回
- この商品を含むブログ (8件) を見る
ノエシスが対象に作用することを『ノエシス的契機』と呼ぶことがあり、ノエシス的契機によって『概念的・感情的・表象的・意思的な意味づけ(意味付与)』が行われるのである。
ノエシス的契機の意識作用には、それ以外にも『確信・推測・判断・計画などの信憑作用』もあり、ノエシスの志向性によって感覚的ヒュレーの意味論的なレベルの認識が成立するのである。『ノエシス的契機』と対になる相関概念として『ノエマ的内実』があるが、ノエマ的内実とは『志向されるもの・志向される意味や概念』のことである。
『ノエマ・ノエシス』は純粋意識の二つの側面であり、志向される内容としてのノエマ的内実は『対象・事物そのもの(物理的なもの)』ではない。ノエマは意識レベルの『志向された内容・意味』であり、ノエシス的契機の多様性に応じて『知覚・想像・表象・虚構・仮構・生き生きとした現実の反映』などさまざまな形を取る。生き生きとした現実を完全に反映した志向内容のことを『全きノエマ』と呼ぶこともあるが、全きノエマを意識するための体系的・技術的な方法論は開発されていない。
[エドムンド・フッサールの現象学と『ノエシス・ノエマ』:2]: Keyword Project+Psychology:心理学事典のブログ
- praxis, poiesis, theoria【アリストテレス?】
- ロス・アシュビー 必要多様度【サイバネティクス?】
簡単な例として、「後だしジャンケン」をとりあげる。相手が先にグー、パー、チョキのいずれかを出したのをみてから、自分の手を出すのである。もちろん、ジャンケンの勝負に勝つことが目標である。相手はいずれの手も出せるものとする、つまり多様度は3である。
戦略としての必要多様度: 出鱈目、矢鱈目、本鱈目
ここで、自分の出す手の数が限られているものとする。自分の多様度が1の場合は、グー、パー、チョキのいずれか、例えばグーしか出せない。この時、勝つことが目標であっても、勝負の結果は「勝ち」、「負け」、「引き分け」のいずれかとなる。つまり、結果の多様度は3となる。
自分の多様度が2となる場合、例えばグーとパーを出せるとする。この勝負では,「負け」はなくなり、「勝ち」か「引き分け」となる。結果の多様度は2となる。
自分の多様度が3となる場合はどうであろうか。相手の手を見て、グー、パー、チョキのいずれでも出せるのである。この勝負では、常に「勝ち」となる。結果の多様度は1となる。
上記の例から分かるように、「後だしジャンケン」で常に勝ち続けるためには、自分の多様度を増加させておかなければならない。
この多様度に関する重要な関係はW.R.アシュビーが「必要多様度の法則」として『サイバネティクス入門』篠崎他訳、宇野書店、1967年の中で述べている。(この原書は1956年に発行されているので、来年は50年目に当たる。なお、アシュビーの書としては『頭脳への設計』山田他訳、宇野書店、1967 年が有名であり、両書ともに格段に面白いし、今でも輝きを失っていない。) 簡単に、この法則を述べておく。
なるほど、わからん…

- 作者: W.R.アシュビー,篠崎武,山崎英三,銀林浩
- 出版社/メーカー: 宇野書店
- 発売日: 1967
- メディア: ?
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: 山田坂仁,W.R.アシュビー
- 出版社/メーカー: 宇野書店
- 発売日: 1967
- メディア: ?
- この商品を含むブログ (1件) を見る
- p.193 ジェローム・ブルンナー 「思考に関する一研究」
ジェローム・シーモア・ブルーナー(Jerome Seymour Bruner, 1915年10月1日 - )は、アメリカ合衆国の心理学者。 一般には教育心理学者として知られているが、認知心理学の生みの親の一人であり、また文化心理学の育ての親の一人でもある。 その生涯を通して20世紀心理学の歴史を体現する巨人である。
ジェローム・ブルーナー - Wikipedia
ブルンナーじゃなくてブルーナーか見つからんわけだ。ま、Brunerだからブルンナーでもブルナーでもブルーナーでも間違いじゃないっちゃないが…人名表記の難しいとこだねぇ

- 作者: 岸本弘,ブルーナー
- 出版社/メーカー: 明治図書
- 発売日: 1969
- メディア: ?
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
- p.231 ルネ・ジラール 『暴力と聖なるもの』(↑に貼った)

- 作者: グレゴリーベイトソン,Gregory Bateson,佐藤良明
- 出版社/メーカー: 新思索社
- 発売日: 2000/02
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 122回
- この商品を含むブログ (63件) を見る
- P.228 カードボックスの比喩
自律的ないしはオートポイエティックなシステムというコンセプトを正当なものとして認容するならば、その場合、システムは本来なら事故に対する否定を含みもっていなければならないはずです。もしシステムが自己否定を含有していないとすれば、システムは完全に自律的ではなく、完全には自足的・自制的(self-contained)ではないことになります。それによってつぎのような問いが立てられます。このシステム理論は自己自身を否定しうるような場を有しているのか否か、という問いです。この問いに関して、わたしはカードボックスにまつわる自身の経験へ立ち戻ってみなければなりません。みなさんのなかにも一部の方々は、幾千枚ものカードを束ねたボックスがあって、つねづねわたしが興味をもったことや、論文で使えるかもしれないと感じたあらゆることを書き付けていることをご存知でしょう。このボックスは今や、かなり膨大なものになっており、もう40年ほどの年季が入っています。このボックスの中に一枚のカードが入っており、そのカードには、これ以外のすべてのカードは間違いだ、と書かれています。他のあらゆるカードと矛盾する議論が、カードのなかの一枚に書きとめられているのです。ところが、わたしがボックスを引き出すと、このカードはどこかへ消えてしまうのです。もしくは、このカードは別の整理番号を与えられて、別の場所へ移動してしまうのです。
これ佐藤先生の本に書いてあったんだっけ?
- p.323 創発 emergent, emergence
創発(そうはつ、emergence)とは、部分の性質の単純な総和にとどまらない性質が、全体として現れることである。局所的な複数の相互作用が複雑に組織化することで、個別の要素の振る舞いからは予測できないようなシステムが構成される。
この世界の大半のモノ・生物等は多層の階層構造を含んでいるものであり、その階層構造体においては、仮に決定論的かつ機械論的な世界観を許したとしても、下層の要素とその振る舞いの記述をしただけでは、上層の挙動は実際上予測困難だということ。下層にはもともとなかった性質が、上層に現れることがあるということ。あるいは下層にない性質が、上層の"実装"状態や、マクロ的な相互作用でも現れうる、ということ。
「創発」は主に複雑系の理論において用いられる用語であるが、非常に多岐にわたる分野でも使用されており、時として拡大解釈されることもある。
創発 - Wikipedia
- 二重の偶発性 double contingency
《偶発的な私の振舞いに偶発的な他者の振舞いが不確定に依存する》こと
http://www.miyadai.com/index.php?itemid=35自尊心を考えてみます。私が「自らが射た矢が確実に命中すること」を自尊心の糧にする場合、自尊心は単一の偶発性に結びついています。的に当たるとは限らないという偶発性に抗していつも的に当てることができれば、私の自尊心が維持されます。
■ところが「矢が命中することを他者がほめてくれること」を自尊心の糧にするなら、状況は一挙に複雑化します。矢が命中すれば他者がほめてくれるとは限らず、ほめてくれるかどうかは多くは、ほめたら私がどう振る舞うか(についての相手の予期)で変わります。
■すなわち、ほめたら私がどう行為するかという他者の予期が、他者が私をほめるかどうかをかを左右するのです。私がほめられようとするなら、私の偶発的(不確定的)な反応行動についての他者の偶発的(不確定的)な予期を、予期しなければなりません。
■私の矢の命中を他者がほめるかどうかという偶発性が、他者がほめたときに私がどう反応するかという偶発性に結びついている──これが二重の偶発性と呼ばれる所以です。この場合、自尊心の維持は、かつてない複雑性に晒されることになります。
■自尊心を維持したい私は、単一の偶発性と違って矢が命中するように精進するだけでは足りず、他者が私の行為をどう予期するか──他者から私がどう見えるか──という偶発性を、コミュニケーション(選択接続)の履歴を用いて操縦しなければなりません。
■別の例です。私が相手に命令しても従うかどうか偶発的です。従うかどうかは、従うか否かで私がどう振る舞うかという私の偶発的反応についての彼の予期に左右されます。従う蓋然性を高めるには、私は彼の予期を予期して、彼の予期を操縦する必要があります。
■拙著『権力の予期理論』に詳述したように、私の権力──私さえいなければ相手が好きに振る舞えるのに私のせいで断念せざるを得なくする力──は、私の手持ちの実物の多寡よりも、私に対する相手のイメージ(予期)を制御する力に依存します。
-
- 偶発性の消去
- 偶発性のやり過ごし
んーわかったようなわからんような…
例えば、次のような状況を思い浮かべてみよう。比較的細い道を自転車で走っているとき、道の反対側からも自転車が来たという状況である。このままだと、自転車同士正面衝突を起こしてしまう。なので、どちらによけるかをお互い判断しなければならない(二重の偶有性の状況)。どちらによければよいかの価値が共有されていないとすると、お互い判断がつかないままであれば、自転車は衝突してしまう。ところが、日常生活ではこのようなケースはなくはないが、たいていの場合、うまく衝突を回避できている。それはどうしてなのだろうか?それは、お互い相手が動いた方向と逆の方向によけるということが、結果としてできているからなのである。この「よけ合い」は、どちらかのちょっとした動きがきっかけで始まる。それがお互いの相互の反応を経て、確実なものとなっていくのである。
このとき、自分が察知した「相手の動き」が、相手の意図して行ったことなのか否かは、問題ではない。相手が「その方向に行った方がいい」と考えたのかもしれないし、たまたま石を踏んでタイヤの向きがずれただけかもしれない。しかし、ここで重要なのは、相手がわずかでもある方向に行ったと認識したということの方である。そのように認識することで、自分は逆の方向に向かうようになり、今度はそれを認識した相手が、先ほどの向きにますますハンドルを切るようになる。
このように、小さな変化の積み重ねによって解決するやり方を説明するとき、ルーマンは、フォン・フェルスターの「ノイズからの秩序」という言葉を引いてくる。別の言葉でいうらば、物理学における「対称性の破れ」(Symmetry-Breaking)の考え方にも通じるといえるだろう。対称的な状況において、わずかに生じた差異が全体の対称性を壊し、非対称性が生み出されるというわけである。
http://socialsystemstheory.blogspot.com/2009/12/blog-post_22.html
この人の説明分かりやすいな。宮台のはわかったようでわからない
『ドン・カルロ』(Don Carlo)はジュゼッペ・ヴェルディ作曲による歌劇。パリ・オペラ座の依頼により、1865年から1866年にかけて作曲、全5幕の歌劇として1867年3月にオペラ座にて初演した(フランス語では『ドン・カルロス』Don Carlos)。
ヴェルディの23作目の歌劇(ヴェルディの創作期間の中では中期の作品に分類される)。原作はフリードリヒ・フォン・シラー作の戯曲『スペイン王子ドン・カルロス』(1787年作)。
ドン・カルロ - Wikipedia
- チャーリーの叔母(Charley's Aunt)はブランドン・トーマスの1892年の笑劇(道化芝居, farce)。1930年にチャールズ・ラグルズ主演、アル・E・クリスティー監督・製作で『のんきな叔母さん』のタイトルで映画化。ジョージ・アボット(『くたばれ!ヤンキース』)台本、フランク・レッサー作詞作曲で『チャーリーはどこだ?(Where's Charley?)』というタイトルのミュージカルにもなっている